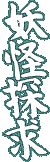
妖怪カタログ・coleader (12/3 16:20) #804 ├ 誰が見ていたか・coleader (12/4 02:05) #810 │└ 貸本屋・タキタ (12/4 21:55) #812 │ └ 江戸の出版事情・タキタ (12/4 23:23) #813 │ └ (追加)筆写し写本 ・タキタ (12/21 01:39) #892 │ └ (質問)発行年度?・タキタ (12/21 01:55) #893 │ └ Re:(質問)発行年度?・ピンヘッド (1/4 18:38) #907 │ └ 日本小説書目年表 ・タキタ (1/8 00:54) #913 │ └ Re:日本小説書目年表 ・ピンヘッド (1/8 11:41) #920 │ └ Re:日本小説書目年表 ・ピンヘッド (1/8 11:47) #921 └ 旧聞「百怪図巻」・タキタ (1/12 05:25) #935 └ Re:旧聞「百怪図巻」・coleader (1/12 09:39) #936 ├ 「百怪図巻」は何年のもの?・タキタ (1/12 21:51) #939 │└ 奥書には・coleader (1/12 23:25) #940 │ └ Re:元文第二丁巳冬日?・タキタ (1/14 00:12) #952 │ ├ 書き方が悪かったです・coleader (1/14 00:41) #954 │ │└ 恐縮です。・タキタ (1/14 01:18) #955 │ └ Re:元文第二丁巳冬日?・ピンヘッド (1/16 10:42) #964 │ └ 元文第二年は1737年・タキタ (1/19 20:44) #977 └ Re:旧聞「百怪図巻」・佐々木 (1/13 07:42) #943 └ 「百怪図巻」パンフレット?・タキタ (1/14 00:40) #953 └ 「百怪図巻」目録・佐々木 (1/14 12:55) #956
| #812 | 貸本屋 | タキタ | 12/4 21:55 |
| → #810 たしか、江戸時代の当時の書物は高価で、 庶民が個人で購入するものではなく、貸本屋で借りて読むというのが日常的であったようです。 金持ちは別でしょう。 きっと、現在の国書刊行会の価格以上に高価なものだったのだと考えられます。 | |||
| #907 | Re:(質問)発行年度? | ピンヘッド | 1/4 18:38 |
| → #893 >当時の書物の奥付けにある出版年度というのがあてにならないという ことになるのですが、このあたりの出版年度の確定というのは、今日 の学問上ではどういう判断をしているのでしょうか? だれか、教えてください。 まず、奥があてにならない、ということはなくて、一応第一級の 資料として扱われます。ただし、いい加減な本屋(海賊版等) が多かったことも事実なので、文献学者はとりあえず諸本の刊記を 綿密に比較します。次に外部的な資料(江戸の出版資料である 割印帳や本屋仲間記録等)をも利用します。さらに刊記にある本屋 の住所や記事内容などに、その本が編集された、または出版され た時期を示すヒントが含まれていることがあります。以上のような 多角的なアプローチによって作成した、日本小説書目年表の類にあ たるのが一般的でしょう。ただし、正直なはなし、この手の本には マチガイも少なくありません。 | |||
| #913 | 日本小説書目年表 | タキタ | 1/8 00:54 |
| → #907 ピンヘッドさん、ありがとうございます。 ところで、「日本小説書目年表」は、この書名で図書館などに蔵書されているのでしょうか? 「そんなもん、図書館で聞きなさい!」と言われれば、それもまた、正しい御教示ですが…… よろしく、お願いいたします。 | |||
| #920 | Re:日本小説書目年表 | ピンヘッド | 1/8 11:41 |
| → #913 通称「小説年表」ですが、 たぶん「日本小説書目年表」が正式名だったと思います。ただし、 古いのと改訂版とがあるので、後者がいいでしょう。怪談ものは おもに浮世草子と読本の項にありますが、この年表にすべてが 網羅されているわけではありません。 | |||
| #921 | Re:日本小説書目年表 | ピンヘッド | 1/8 11:47 |
| → #920 いいわすれましたが、 比較的どこにでもある本です。書誌コーナーとか。総記とか。 | |||
| #939 | 「百怪図巻」は何年のもの? | タキタ | 1/12 21:51 |
| → #936 『百怪図巻』って、いつのものと判断すればよいのでしょうか? 江戸末期としか「週刊朝日」には書いていないのです。 | |||
| #940 | 奥書には | coleader | 1/12 23:25 |
| → #939 奥書には「元文第二丁巳冬日」とあるので これが正しいとすれば1737年ですね。 吉川観方『絵画に見えたる妖怪』からの情報です。 | |||
| #952 | Re:元文第二丁巳冬日? | タキタ | 1/14 00:12 |
| → #940 「元文第二丁巳冬日」は、西暦1737年だと判断できます。 「巳」=「ヘビ年」だし、「甲乙丙丁」の「丁」に該当する「巳(へび)年」だからです。その冬の日という意味でしょう。 ところで、この「第」って何なんでしょうか? 「元文2年」を「元文第2年」という表記って? 判る人は教えてください。 | |||
| #954 | 書き方が悪かったです | coleader | 1/14 00:41 |
| → #952 奥書に「元文第二丁巳冬日」と記述がある というのが『絵画に見えたる妖怪』からの情報で、 1737年というのは私の判断です。 この奥書の記述が正しければ、という意味で書き込みしました。 紛らわしい表現ですいませんでした。 | |||
| #955 | 恐縮です。 | タキタ | 1/14 01:18 |
| → #954 「元文第二丁巳冬日」を1737年というのは正しいようです。 阿南市史編纂室も解釈は、1737年説でした。 「はてな?」と思われたのは「第」という文字に関してです。 歴史学の大学教員なども学識経験者もスタッフですから数日のうちには解答を見出すでしょう。 つまり、「牛鬼」調査関連で、阿南市史編纂室にも「牛鬼」を報告しておいたのです。 | |||
| #964 | Re:元文第二丁巳冬日? | ピンヘッド | 1/16 10:42 |
| → #952 元文の第二番目の年、というだけのことで、 元文二年というのと同じことです。 | |||
| #977 | 元文第二年は1737年 | タキタ | 1/19 20:44 |
| → #964 福岡市博物館からの回答でも、元文第二年は、1737年でした。 ありがとうございます。 なお、福岡市博物館の話でも、「週刊朝日」が「百怪図巻」の成立(?)を「江戸後期」と書いてあるのは誤りで1737年、つまり「江戸中期」が正しいとのことでした。 | |||
| #943 | Re:旧聞「百怪図巻」 | 佐々木 | 1/13 07:42 |
| → #936 昨年10月刊行予定でしたが、某先生の原稿がまだできてないんです…。このまま行くと企画自体がお蔵入りしそうでして…。 | |||
| #953 | 「百怪図巻」パンフレット? | タキタ | 1/14 00:40 |
| → #943 「週刊朝日」の1997年8月15・22日合併号が唯一の資料になるのでしょうか? 一般人たる全国の福岡県外の人の接することができる「百怪図巻」の? 1998年夏に福岡市博物館での公開予定と、「週刊朝日」の1997年15・22日合併号に紹介されている展覧会の時にパンフレットって作っていないのかなあ? | |||
| #956 | 「百怪図巻」目録 | 佐々木 | 1/14 12:55 |
| → #953 見に行きました。チラシはありましたが、私が行ったときには目録は無かったです。今は…わかりません。 | |||